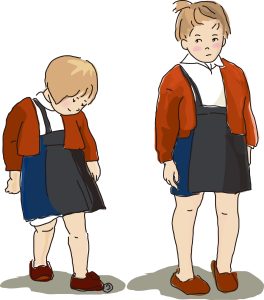インタビューの後編では、大学受験や就職活動、さらにはケアの現実と向き合う中で、髙橋さんがどのように人生の選択をしてきたのか、その道程についてお届けする。
ケア生活が大きく影響した進路選択
ー高校生の頃はいかがでしたか?
中学校での生活とあまり変わらない生活でした。私が中学3年生~高校2年生くらいまで、母親はアルコール依存症のために通院をしていたのですが、病院から処方された薬の服薬管理は私がしていましたね。その後、母親の症状は改善していき、私が高校を卒業する頃には落ち着いていました。今は通院しなくても大丈夫な状態になっています。
当時の私としては「母親がアルコール依存症になったのは私のせいじゃないか」「原因がわからないと根本的な解決にならないのではないか」という思いもあり、母親がアルコール依存症になってしまった原因を知りたかったんです。でも、母親は自分の状況を話すのが難しく、原因を知ることができない状況でした。そんな状況に当時は複雑な気持ちを抱えていましたね。今は結果として症状は落ち着いているので良かったと思っています。
ーお母さんの治療の裏で、色んなことを考えられていたんですね。お母さんの依存症が落ち着いた、大学受験の頃はいかがでしたか?
勉強で苦労したというよりも、進路を決めるのにとても時間がかかりました。進学先を絞る際、私が家の近くの学校ばかりを候補に挙げるので、先生に「どうして家の近くばかりなの?」と聞かれることがありました。その時、母親のことを先生に話したら、先生は「お母さんはお母さんだから、自分のことは自分で頑張ると思うよ」と言ってくれたんです。
それは先生なりの「家に縛られずに自分の人生を生きなさい」というメッセージだったと思います。でも当時の私は「先生は実際にお母さんを見ていないのにどうしてそんなことが言えるんだろう」と感じていました(笑)。
進学先としては、障害を学ぶ学部に進学したかったのですが、そのための面接練習で母親のことを話すと、涙が止まりませんでした。特に悲しい出来事を思い出したわけではないのですが、今まで母親のことを話す機会がなかったので自然と涙がこぼれてきたんです。とにかく、大泣きしてばかりでした。

結局、その大学には落ちてしまいましたが、面接を担当してくれていた先生は「落ちて良かったと思う。面接練習で泣いてしまうくらいだから、毎日障害について勉強するのはあなたには辛すぎたと思うよ」と言ってくれたんです。それもそうだなと思いつつ、最終的には家の近くにできた医療系の大学に進学することになりました。
自分の就職先と母親の施設探しに奔走することに
ー就職活動はいかがでしたか?
大学生の頃は、父親が1人暮らしを勧めてくれたのもあって、実家を離れていました。そんな中で、私が大学3年生の時に母親が階段から落ちてしまったことがあったんです。その時は、母親の生活環境を整えるために週末に実家に帰り、平日また一人暮らしの家に戻るという生活を送っていました。そうした生活を通して初めて「母親はずっと見守っていなければいけない人なんだ」「障害福祉サービスを利用した方がいいかもしれない」ということにやっと気づいたんです。そういう訳で、私の就職活動のタイミングと同時に母親のデイサービス探しをするようになりました。
この両立が本当に大変だったんです。自分の就職活動よりも母親のデイサービスの見学の方が多い時もあったり…(笑)。母親の希望や状態に合う所がなかなか見つからず、施設選びにとても苦労しました。最終的に良いところが見つかり、今は週に5日デイサービスに通っています。私自身も、大学から就職活動を催促される中で、ようやく就職する年の1月に就職先が決まりました。
ふと感じた違和感。母親と自分のために退職を決断
ー今、お仕事はどうされているのでしょうか
仕事は2年前に退職しました。当時、母親の介護度が上がり、よく家で転んでいたんです。私の出勤前に転んで出血した時は、母親を病院に連れて行ってから遅れて出勤するということもありました。そんな日々が続いて自分の中で「これでいいのかな」という思いが芽生え始めたんです。
世間的にはこれが介護離職だと思うのですが、自分の中では介護のために離職したとは考えていませんでした。というのも、どうしても介護離職にネガティブなイメージがあったんです。あまりよくないことだとも思っていました。でも私は、仕事をやりながらあれもこれもやってというよりも、ケアや自分のことを含めて考える時間が欲しかったんです。それを介護のせいにしたくなかった…「やりたいことのために仕事をやめるんだ」と自分に言い聞かせていました。
ー実際に退職されてから心境に変化はありましたか?
最初の1年はケアに向き合うことがとても辛かったです。デイサービスの車がきても私が居留守を使ったりしていました(笑)。それでも2年目には、朝デイサービスの人がきたら「お願いします」と見送って、帰りも「ありがとうございます」と出迎えられるようになったんです。そこは心境の変化かもしれません。仕事を辞めた当時はどうにも「介護離職した」という現実を受け入れられませんでした。母親のために仕事を辞めたけれど、母親とは顔を合わせたくない…そんな状態でしたね。
あと、私が仕事をしている時から母親が頻繁にタバコを吸っていたんです。火の始末も心配で家に帰ったら家が燃えているんじゃないかと考えたこともありました。タバコをやめさせるために禁煙外来に連れて行ったこともあったんです。去年の1~2月頃にはようやく母親からタバコをとったり、お金を渡さないようにしたり、タバコを買いに出かけないように止めたり…といったことができるようになりました。これもできるようになるまでやはり1年くらいはかかりましたね。
今では、母親をショートステイに預けられるようにもなりました。ゆっくりではありますが、ようやく向き合えるようになってきて良かったなという気持ちです。

一方で、ずっと母親を見ているのは疲れます。「倫理的に、出かけないように止めるという行為はしてもいいのだろうか」「虐待じゃないのか」「タバコで家を燃やされそうになるのは私が心配していることだから、私が家を出て行ったらいいんじゃないか」と色々考えることもあり、そういう気持ちの面も含めてケアに対する葛藤はあります。
ー髙橋さんの今後の展望を教えてください
母親が施設に入所してくれないと自分の人生を歩めないと思っていたので、今まで施設探しをしていたんです。現状は、入所という形はとっていないのですが、ショートステイに毎回繰り返し2週間ほど行ってもらっています。ショートステイに行っている間はデイサービスに行くことができません。デイサービスが大好きな母親はそれが不満でショートステイに行くと「いつ帰れるのか」と電話をかけてくることがあります。
そういうことがあると「これは果たして母親にとってもいいことなのか」「デイサービスも利用できるグループホームのような所が良いんじゃないか」「母親の望みを叶えられる生活があるのではないか」と考えることがあります。1日も早く施設に入れたいと思っていましたが、その決断をして後悔をしないか今も悩んでいます。
この状況で私がフルタイムで働こうと思うと難しく、ショートステイ先でもいつ何があるかわかりません。母親をショートステイに預けられることを前提にしても、私が自分のことをやるとなった時に難しいのが現状です。自分のことを考えるのが二の次になってしまうのですが…。母親がデイサービスを辞めずに、私自身も自分の時間を確保できていったらいいなと思います。
ー最後にヤングケアラーの方にメッセージをお願いします
「ヤングケアラー」という言葉が広がって、自分の気持ちや状況を人に話しやすくなる機会が増えることはいいことだと思います。一方で、私はこの言葉を初めて知った時、自分のことだと思えなかったんです。むしろ『私はヤングケアラーです』というのが嫌でした。
それでも「ヤングケアラー」という言葉を頼りにしたら、自分の似た境遇の人と出会うことができました。それが自分にとっては良かったと思います。それに加えて「ヤングケアラー」という概念は、ヤングケアラーだけでなく家族も、ケアをしてない人も、それぞれが望む生活を送れるようにする1つの考え方だと思います。
なので「ヤングケアラー」という言葉に縛られすぎないようにしてほしいです。自分にとって良いことがありそうだ、自分の現状をうまく話せそうだと思った時にこの言葉を上手く使ってほしいと思います。

ー貴重なお話ありがとうございました
終わりに
EmpathyMediaでは、
・ヤングケアラーの方
・元ヤングケアラーだった方
へのインタビューを行っています。ご興味を持っていただいた方はお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
公式X:@EmpathyMedia4u
EmpathyMediaは「生きにくいを、生きやすく」の株式会社Empathy4uが運営しています。
株式会社Empathy4uでは、ヤングケアラー実態調査、SNS相談、オンラインサロン、支援者向け研修などヤングケアラー支援を積極的に行っています。お問い合わせは会社HPからご連絡ください